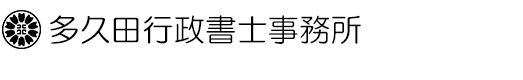「相続させる」旨の遺言とは?
遺言書は、記述の方法や遺言できる内容について、厳密な決まりが定められています。遺言によって特定の人などに財産を移転することを遺贈といいます。
遺贈は、誰に対してもできますが、特定の財産を配偶者や子などの法定相続人にする場合は、「相続させる」と表記するようにしましょう。
「相続させる」と「遺贈する」の違い
民法には相続人の定めがあり、認知するような場合をのぞけば、遺言によって新しい相続人を定めることはできません。
遺言書で法定相続人以外の者に財産を譲る場合は、相続ではありませんので「遺贈する」と表記することになります。
遺贈については、包括遺贈と特定遺贈があります。 →ブログ「相続・遺贈・死因贈与の違い」
包括遺贈の場合は、相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)。
問題になるのは、遺言書で法定相続人に財産を移転させる場合です。この場合、「相続させる」「遺贈する」いずれの表記も可能です。
「相続させる」趣旨の遺言については、最高裁判決(平成23年4月19日判決)により、①遺産の分割方法を指定した遺言であって、かつ、②何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されるとされています。
何らの行為を要せずというのは、相続人による遺産分割協議を必要とせず、直接、権利が移転するということです。
「遺贈する」場合には、相続人に対して不動産などを譲る特定遺贈で、相続との違いが生じることになります。
遺贈者の死亡により直接、権利が移転することは共通していますが、仮に受遺者がその不動産がほしくない場合などは、いつでもそれを放棄することができます(民法986条1項)。
多くの場合で、遺言書には「相続させる」という文言が使われてきましたが、これにはいくつかの実務上の利点があったためです。
「相続させる」遺言の実務上の意義
実務上では、相続人に「相続させる」とする文言には、「遺贈する」とした場合と比較して、次のような違いがあります。
〇不動産の登記について単独で登記ができる
遺贈では、登記するためには、全相続人(または遺言執行者)と共同申請する必要がありますが、相続では当該相続人が単独で申請できます。
〇第三者に対して、不動産取得の登記することなく対抗することができる
遺贈では、所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要ですが、相続では登記を経なくても遺産の取得を第三者に対抗することができます(最高裁平成14年6月10日判決)。
〇不動産などの賃借権を承継した場合、賃貸人に承諾を求める必要がない
遺贈によって不動産などの賃借権を取得した場合は、包括遺贈・特定遺贈ともに賃貸人(地主・家主)の承諾を得る必要がありますが、相続の場合は不要です。
このほかにも、かつては以下のような違いがあり、「相続させる」場合の方が有利でしたが、現在は両者に違いはありません。
●登録免許税の税率が、以前は遺贈の場合は不動産評価額の1000分の25、相続は1000分の6で相続の方が有利でした。現在は、法定相続人に対する遺贈も相続も、ともに1000分の4(0.4%)で違いはありません(平成18年4月1日以降)。
●農地法では、遺贈の場合は農地法第3条による当道府県知事の許可が必要でしたが、法改正により、相続の場合と同様に不要になりました(平成24年12月14日以降)。
ただし、いずれの場合も取得後は、農地法3条の3による農業委員会への届出が必要です。
このように、「相続させる」旨の遺言には、実務上の利点があることもあって使用されてきました。
「相続させる」遺言と代襲相続
「相続させる」旨の遺言では、次のような点に配慮する必要あります。
遺言者より先に、遺産を相続させるとされた推定相続人が死亡した場合は、推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、効力を生じません(最高裁平成23年2月22日判決)。
つまり、子である推定相続人が親である遺言者より先に死亡した場合、特定の遺産について「相続させる」と書いただけでは孫への代襲相続は発生しません。
こうした場合を考慮して、「長男〇〇が遺言者より先に死亡した場合は、〇〇の長男△△に相続させる」といった予備的遺言も必要になってきます。
「相続させる」の文言は、公証人が作成する公正証書遺言の場合は、表記にも配慮されますので特に問題は生じないと考えられます。
自筆証書遺言を自身で書かれる場合などは、このような表記にも十分に注意を払って書くようにしましょう。